専門コラム パワハラ防止法対策:社長がハラスメントに興味がない場合の予防策
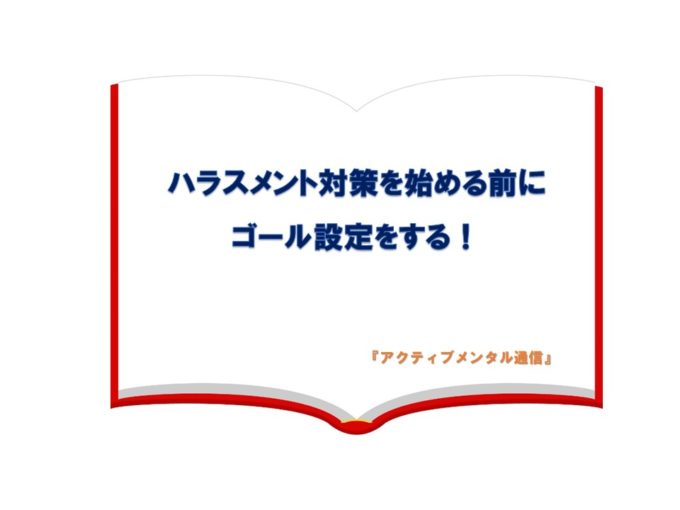 先日、ある経営者の方からご相談をお受けしました。ストレスチェックのシステムをご提供されている企業の方です。
先日、ある経営者の方からご相談をお受けしました。ストレスチェックのシステムをご提供されている企業の方です。
ハラスメント予防にも力を入れようとされているとのことで、ハラスメント予防コンサルタントとして研修や相談者対応を行っている弊社にご相談があったのです。
お取引先の企業の実状をお伺いすると、「経営陣が全くハラスメント対策に興味がないん
ですよ。それどころか、創業者の会長自ら、セクハラやパワハラまがいの言動がひどくて・・。
社長は2代目なのですが、それを見て育ってきているので、ハラスメント言動はあまり目立たない人なので、それだけは安堵しているのですけどね。
中小企業も2022年からはハラスメントに関する予防措置を行うことが義務化となるわけで、
何か対策を打とうと考えているものの、何から始めればよいのか全くわからない。どうしたらよいでしょうか。」とご相談を受けているとのこと。
正直、ありがちなことだなと思いつつも、放置しておくことは出来ません。とはいえ、すぐにハラスメント研修をやり、ハラスメントに関する知識だけを得たところで、解決にはほど遠いという結果に終わります。
というのも、そもそも経営陣がハラスメントは存在しないと考えているからです。そんな
企業で働く社員も、「うちの会社で研修をやっても何も変わらない。」と半分諦めていることも多いものです。
そんな中で、パワハラとは・・・セクハラとは・・・
という知識研修を行ったとしても、所詮他人事に終わってしまい、学んだ知識も一過性のものとして終わってしまうことでしょう。
なので、ご相談に対しては、ハラスメント研修をこの段階で提案してはいけないことを
お伝えしました。
では何から始めればよいのか。
まず取り組むべきことは、経営陣にハラスメントがいかに企業のリスクとなり得るのかという認識を持ってもらうということです。
そして、企業義務として何をすべきなのか、求められているのかを共有することが先決です。
啓発や教育だけではなく、相談窓口の設置や、ハラスメント案件が発生した後の迅速な社内対応なども求められているからです。
まずはハラスメント対策を行うにあたり「導入セミナー」のような経営陣限定の研修をしっかりと行うことが先決です。
さらに大切なことは、この共通認識を持った後、なぜ自社でハラスメント対策をするのかという大義名分を言語化するということです。
義務化になったからやっている・・・というのでは、予防策も形骸化し、そもそもハラスメント予防をしっかり行うというカルチャーは根付かないでしょう。
例えば、自社のゴールを「社員がイキイキ働き互いを尊重できる職場にする」「ハラスメントをなくして生産性向上を図る」などを決め、それをハラスメント対策の合言葉にするのです。
ゴールを見失うと、対策の内容もブレてしまうからです。
そして、ハラスメント対策を導入していくにあたり、1年目の目標、2年目、3年目の目標と目標設定をし、それぞれに大まかなスケジュールやすべきことを考えることが重要です。
それらを決めてから、ハラスメント研修はいつ、どのタイミング対策で行うのかを決めるのが良いでしょう。
ハラスメント研修だけを実施し、ハラスメント予防をしているつもりになってはいけないということも同時にお伝えしておきます。
御社では十分なハラスメント対策が出来ていますか。
正しい手順で、ハラスメント予防が根付くような取り組みをしていますか。

