専門コラム 社員のやりがいを搾取する 組織内の見えない壁がもたらす弊害
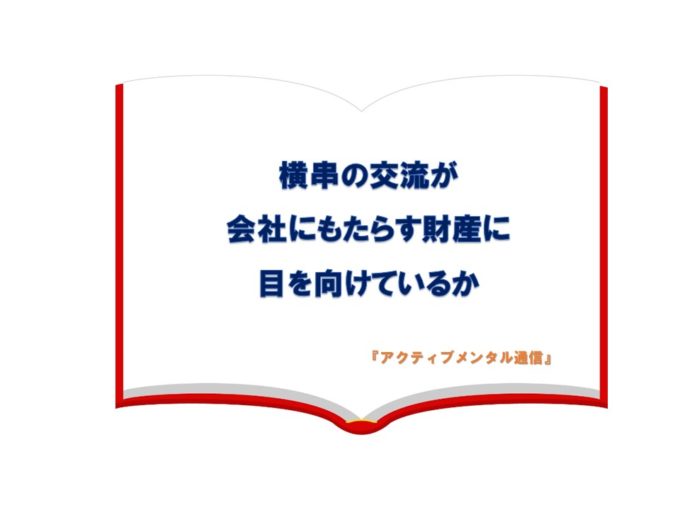
第87話: 社員のやりがいを搾取する 組織内の見えない壁がもたらす弊害
イキイキ働く社員が育ち、働きがいのある職場環境づくり、活気ある組織風土づくりを専門に行っている当社には、日ごろより人材育成に対する意識が高く、すでになんらかの取り組みを行っている企業の社長さんから様々な相談をお受けしております。
先日の御打ち合わせ時に思い出したのが、以前属していた組織で関わっていた数々のプロジェクトのことでした。新薬の上市に向けて、マーケティング担当者を中心としたプロジェクトがつくられておりました。患者会との強いパイプを持っているという立場上、どのプジェクトにも関与を求められていたのですが、毎回、疑問に感じていることがありました。それは、前回のプロジェクトの成功点や課題などが、マーケティング部内で共有されていなかったことです。
正確にはマーケティング担当者間で共有されていなかったのです。まさに縦割り組織の弊害でしょう。自分の担当する薬剤について相当な思い入れがあったとは思いますが、なぜか、昨年上市したプロジェクトの担当者と情報やノウハウを共有しなかったのです。隣の課で、毎日顔を合わせる同僚だったのにも関わらず、です。もっとオープンに、どんなことに苦労したのか、どんな点がうまく行ったのかをコミュニケーション出来ていれば、それは社内の「知識・経験」として蓄積されていたに違いないのです。
が、知識や経験の蓄積ではなく、「担当者個人の実績」という認識の方が勝っていたのというわけです。確かにプロジェクトを成功させた暁には、担当者は評価され、その実績を買われ多く者が昇進していきました。ですが、今、振り返ってみると、会社としてはなんともったいないことをやっていたのか、という思いが湧いてくるのです。
担当者が離職した場合は、その「経験」が社内に残りません。プロジェクトチームで培った「ノウハウ」が蓄積されない場合、次の担当者は、まさにゼロからプロジェクトをスタートさせなければならないのです。それが「やりがい」だったと言われればそうかもしれませんが、毎回チームとして関与している身としては、毎回、新しい担当者にイチから説明するということを繰り返していたわけです。
================================
自分の所属している部署だけが良ければ問題ないという誤った仲間意識
================================
このようなやり方が放置され続けると、「自分が所属している部署」の利益のみを優先するという事態に発展してしまうことがあります。同じ会社なのに、隣の課がやっていることについては、「関心がない、興味がない」だけではなく、「自分の部署、部課だけで良ければそれで問題ない」という意識が蔓延していきます。
また、毎回同じことをイチから説明し、やらされる立場としては、間違いなく「やりがい」を感じなくなっていきます。プロジェクトチームのリーダーだけが、実績を作るために意気込み、頑張っても、まわりがついていけないということも起こりうるのです。
この時、トップが「もっと情報を共有するように」と言ったところで、変わりません。担当者本人は、自身の評価と関係あるわけですから、なおさらです。解決策として社長が考えるべき方法の一つは、横の交流を促進するということです。もちろん、業務上のジョブローテーションなども含まれますが、普段から、業務以外の場面においても人的交流、情報交換などが活発に積極的になされるような取り組みを行うということです。
実際の取り組み方法については、コンサルティングの中で説明させていただいておりますが、「これがたったひとつの解決法である」というものではなく、個々の組織の事情により異なり、さらにスモールステップとして取り組めるものから始めることが重要なのです。
今週の提言
横串の交流が会社にもたらす財産に目を向けているか
最新コラムを見逃さないよう、メルマガにご登録ください。
ご登録はこちらから。

